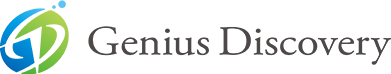情報の取捨選択
湘南台教室です。
今日は、中秋の名月。子ども達に国よってお月さまの月の模様が違うことを伝え「どう見えるか教えて。。」とお願いしましたが、お月さまで、どうですかね?
先月から藤沢市主催の自閉症についての研修を受けています。
講師の方が言われる、「伝える側の取捨選択」の大切さを実感しています。
Geniusの研修でも短時間に覚える記憶には個人差がある。例えば「嵐、織田信長、イチゴ」といったことを覚えるに3つの単語を別々に覚えるのと、「嵐の日に織田信長がイチゴを食べた」と1つで覚えるのではワーキングメモリーに差が出ます。
私たちがいかに伝える事が取捨選択するかが、大変重要になります。
例えば「雨はなぜ降る?」と質問されたら
1. 雲の中のちいさなつぶがどんどんあつまって大きくなると、重くて浮けなくなり、ぽたっと落ちる。それが雨だよ。そして空がもっともっとつめたいと、水のつぶが氷になって雪(ゆき)やあられになることもあるよ。
落ちた雨は地面にしみたり、川になって海に戻る。太陽でまた空へのぼって、これをくり返すんだ
2. 雲の中の水のつぶがあつまって大きくなると落ちるんだよ
1と2どちらが子どもに伝わりますか?
おそらく子どもは 2 の回答で「ふーん」となるのではないでしょうか?
これが伝える側の取捨選択です。たくさんの情報を あれも、これも 知ってほしいと伝えしまいがちですが、伝える側がどれだけ取捨選択できるか。。。
興味があるなら続く会話であり、以外の子に対して「今は必要のない情報」であり、子どものワーキングメモリーに不可がかかり、必要な情報や言葉が記憶されない。
支援をしている時は、支援者側も頭フル回転です(笑)仮説をたて準備をしていますが、反応が違うこともあるので、そんな時、いかに臨機応変に対応できるか。。。 お互いに脳のネットワークをひろげています(#^.^#)